機動戦士ガンダムAGE 〜MEMORY OF EDEN〜のプレミアム上映会に行ってきたぁ ― 2013年06月30日 06:54
このバンダイナムコ未来研究所は以前、松下電器産業が入ってたビルで、私も何度か打合せに来た事がありました。 また、今回行われた上映会場のビデオプロジェクターは何度か改修の作業をした事もある思い出の場所。 そんな所でガンダムAGEが観れるなんて、自分の中で何か感慨な気持ちになってました。
集合時間前に到着。 入り口には「機動戦士ガンダムAGE 〜MEMORY OF EDEN〜」のプレミアム上映会の案内立て看板が置かれてました。
入場では当選案内のメールを確認され、自身の名前も確認されました。
その横にはプレミアムバンダイから発売されるガンプラ等が展示されてました。
前列左右 HGガンダムレギルスMEMORY OF EDEN 申し込み受付中
後列左 MGガンダムAGE-1 2号機 申し込み受付中
後列右 MGガンダムAGE-2 特務隊仕様 申し込み受付中
会場のスクリーンには「機動戦士ガンダムAGE 〜MEMORY OF EDEN〜」プレミアム上映会が投影されてました。
今回はこの様な席で観る事ができました。
センターより上手側でしたが、スクリーン自体も特に問題なく観える席でした。
女性の方が若干多いくらいの比率で、子供さんもちらほらといる程度。 年齢層はお若い方が多かった様に見受けられました。
今回の上映会はトークショーを挟んだ前半と後半の2部構成で上映されました。
司会は小林治氏
第一部の上映前に小林氏による諸注意等の説明
ガンダムインフォで応募されていた「ガンダムAGEオリジナルMSガンプラコンテスト」の特別賞の発表
第一部の上映後、綿田監督、小川プロデューサーが登壇されトークショー
第二部の上映後、綿田監督、小川プロデューサー、千葉道徳氏が登壇、トークショー
ネタバレ禁止と言う事でここでは書く事ができないのですが、ネタバレしない程度に発言するのはOKとの事。
構成は大きく分けて3部構成。 1部と2部で前半。 3部が後半。
いずれも新作カットは豊富にあり。
ほぼゼハートの視線での内容。
小川プロデューサーからの発言でTV放送48話でやり切れなかった事を詰め込んンだ内容になってると。
TV放送のまとめと高を括ってたのですが、どうしたものか最後は感動。 会場の大半がすすり泣く程の状態で、上映後のトークショーでは小林氏から「監督!泣いてましたよ」、綿田監督「ありがたいですね」と。
これしか書き様がないのですが、新作と言っていい程の内容に仕上がっており、時間の長さを感じさせずいい流れでした。
今回会場で配布されたプログラムチラシです。
2013年上半期ガンダム書籍ベスト ― 2013年06月30日 13:51
そんな事で、半年に一度のガンダム蔵書が勝手に選ぶ上半期
ガンダム書籍ベスト5の発表です。
2013年1月1日~6月30日まで出版されたガンダムの
関連書籍が対象に選びました。
総数 93冊。
設定資料 その他部門対象数 53冊。
小説 他部門対象数 3冊。
コミック部門対象数 37冊。
過去に行ったガンダム書籍ベスト5です。
2011年ガンダム書籍ベスト5
2012年上半期ガンダム書籍ベスト
2012年ガンダム書籍ベスト5
【小説 他部門】
第1位
新機動戦記ガンダムW フローズン・ティアドロップ
7巻 寂寥の狂詩曲 (上)
8巻 寂寥の狂詩曲 (中)
隅沢克之/著 角川書店発行
プリベンダー5とMCファイル5が収録され、過去編だったり
現在・未来編と少し頭がついていかなくなってしまいますが
展開テンポもいいし、いい感じにまとまっているので
この順位にしました。
第2位
俺の艦長
廣田恵介/著 一迅社発行
ガンダム以外にヤマトシリーズやマクロスシリーズ等の
艦長をまとめた書籍になります。
ガンダムからはブライト・ノア、パオロ・カシアス、
リード、ガデム、フラナガン・ベッケナー、
ビーチャ・オーレグ、エマリー・オンス、ロベルト・ゴメス、
オットー・ミタス、スベロア・ジンネマン。
以上11名の艦長の紹介が掲載されています。
まあ、あまり艦長視点での書籍というものがなかったので
この順位としました。
第3位
ガンダムがわかれば世界がわかる
多根清史/著 宝島社発行
2005年に発行した同著者「機動戦士ガンダム研究叢書
宇宙世紀の政治経済学」と同じ内容。
経済学の著書は難しいです。
この半期に発売された書籍が3冊しかなかったので、以後の
順位はありません。
【設定資料 その他部門】
第1位
安彦良和 アニメーション原画集「機動戦士ガンダム」
安彦良和/著 角川書店発行
機動戦士ガンダム(1979年作)のアニメーションで使用した
原画が多数掲載。
思い出のシーンの原画が掲載されており、安彦先生の描いた
線は観ているとうっとりするほど素晴らしいです。
今年の1位は間違いなし、私の所蔵している書籍の中でも
上位に入る程素晴らしい仕上がりになっております。
第2位
超・大河原邦男展
-レジェンド・オブ・メカデザイン-図録
兵庫県立美術館、産経新聞社発行
今年の3月から兵庫県の兵庫県立美術館で開催された
超・大河原邦夫展の図録になり、その展示物のほとんどが
この図録に収録されており、解説等も掲載しています。
ガンダムだけではないのですが、デザイン画やポスター画
等はこの図録を見るだけでも素晴らしさが伝わると
思います。
第3位
SDガンダムの常識 武者・騎士・コマンド編
双葉社発行
久しぶりにSDガンダムの資料集が出版され、内容的にも
よくまとまっており、今からSDガンダムに入ろうとか
一部のSDガンダムしか知らなく他のSDガンダムも知って
みたいって方にもお勧めです。
第4位
機動戦士Zガンダム外伝
ADVANCE OF Z刻に抗いし者エゥーゴの蒼翼
ビジュアルブックコンプリートファイル
アスキー・メディアワークス発行
電撃ホビーマガジンに連載された同タイトルのまとめと
なります。
小説では細部まで書かれていないMSやMAのデザイン、
武装等が立体化の作例が掲載されているので、これは
これで結構いい資料ではないでしょうか。
第5位
機動戦士ガンダムUC メカニック&ワールドep4-6
双葉社発行
同タイトルのとおり、ガンダムUCのepisode4~6までの
設定資料が掲載されており、中でもジオン残党軍のMS
設定は必見じゃないでしょうか。
私はバンシィ好きなので、この資料はとても好きです。
次点
MEAD GUNDAM [復刻版]
復刊ドットコム発行
今年の初めはこの書籍が話題でした。
それは2000年に発行された同書籍ですが、発行部数が
少なかった事から巷ではプレミア価格が付く程の人気。
この復刊を機に手にされた方は多いのではないでしょうか。
【コミック部門】
第1位
ガンダムEXA 4巻
ガンダムEXA 5巻
ときた洸一/著 角川書店発行
4巻ではクロスボーン・ガンダム編。その終わりから5巻に
かけてララァが絡むガンダム編と。 そしてフォンが登場し
874への・・・。くぅぅ。痺れちゃいます。
特にこの5巻は感動するのでお勧めです。
第2位
西原理恵子の人生画力対決 5
西原理恵子/著 小学館発行
去年の4月に行われた
「西原理恵子の人生画力対決ライブ
~安彦良和SPECIAL~
逆襲のサイバラ少佐!めぐりあい渋谷(そら)!!」の
内容が掲載。
安彦先生の対決画は必見です(笑)
第3位
機動戦士ガンダム
MSV-R ジョニー・ライデンの帰還 MATERIAL-F 6
Ark Performance/著 角川書店発行
毎回上位に入るArk Performance先生の書籍は申し分の無い
画と内容で楽しませてもらってます。
ほんとこれほどのクオリティーを毎回描かれているのが
すごいですね。
第4位
機動戦士ガンダム 黒衣の狩人
万乗大智/著 小学館発行
1巻完結です。遣る瀬無い気持ちと最後には切なく。。。
感動すること間違いなし。
ヅダの活躍も必見ですよ。
第5位
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY Re:Master Edition 1
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY Re:Master Edition 2
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY Re:Master Edition 3
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY Re:Master Edition 4
ときた洸一/著 角川書店発行
1巻と2巻は同時に発売になり、この書籍をもって
ときた先生ご自身のガンダム書籍50冊発行を達成され
ました。 おめでとうございます。
タイトルのリマスターと入っている事でお解かりかと思い
ますが、2003年から発行されたガンダムSEED ASTRAYの
再編集版になり、時系列を追った内容に変更されてます。
ロウと劾、レッドフレームとブルーフレームの活躍を
再認識できます。







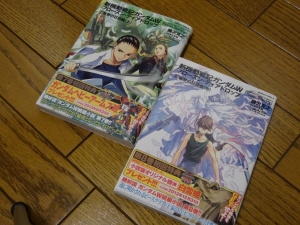



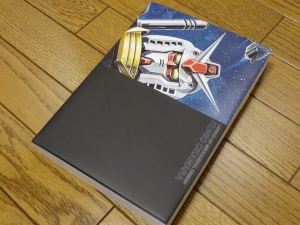

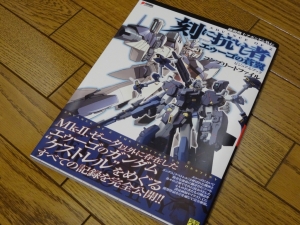
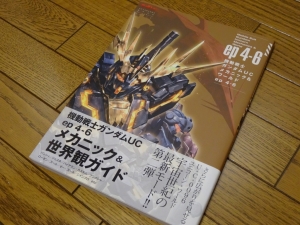
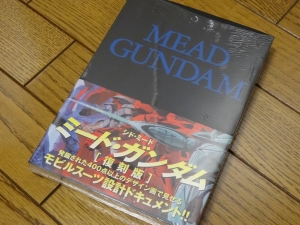
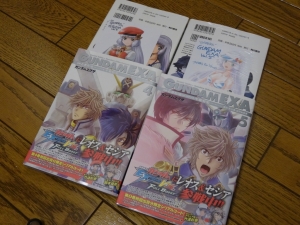


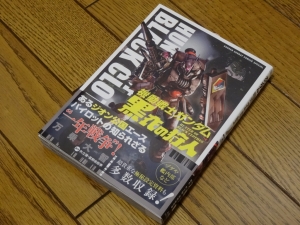

最近のコメント